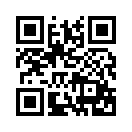2020年02月16日
循環型農業の理想を目指す糸満農水苑
FMたまん毎週土曜日12時〜12時55分放送2月15日のビタミンFMは農水苑の代表の前田英章さんをゲストに放送いたしました。
農水苑は一言でいうとどんなところなのでしょうか?いきなりこんな質問から番組はスタート致しました。

農水苑について語る前田英章さん
琉球新報2019年2月19日に次の様な記事が掲載されていました。農水苑のごく一面なのですが、引用させて頂きました。
糸満市新垣で外国産飼料を使わず、自ら作った発酵飼料で鶏を育てて、卵を販売している「農水苑・虹」(前田英章代表)の、新しい卵のパッケージが完成した。8月16日、デザインの基になった絵を描いた子どもたちを「虹」に招いて、お披露目会が開かれた。

お披露目会に参加した子どもたちとデザインを担当した「デコール」の瑞慶山成人さん(右端)と亜矢子さん(右から2人目)、農水苑・虹の前田英章さん(中央)=糸満市新垣の農水苑・虹
新しく完成したパッケージは「虹」に日頃から遊びに来ている子どもたちが、「虹」で働く人たちや鶏をイメージして書いたイラストを基に、豊見城市でデザイン事務所「デコール」を営む瑞慶山成人さん(39)亜矢子さん(39)夫妻がデザインした。

パッケージを手に取った藤井橙子さん(6)は「イラストがかわいいパッケージになってうれしい。お店に並んでいるのを見るのが楽しみ」と話した。
前田さんは「子どもたちのエネルギーがいっぱい詰まった絵で包まれた卵は、食べる人も元気になると思う」と顔をほころばせた。
亜矢子さんは「子どもたちだからこそ描ける絵がとてもすてきだった。いろんな人に手に取ってもらいたい」と話した。

冒頭の質問は言い換えれば、前田さんが目指す農業とは何かという事になる。
1ー作物本来の力引き出す
教育や環境、平和、エネルギーなど、現代が抱える問題に対処するには、新しい価値観でライフスタイを再構築するべきだと前田さんは考えた。循環型で化学肥料を使わない、自然に無理を押し付けない農業で、本来の力を引き出そうと考え実践する農業を目指している。
2ー科学的な目を持って
農水苑・虹の畑では、化学肥料や農薬を使わない代わり、堆肥づくりや海砂を土にすき込む伝統的な土壌づくり、大陰暦(旧暦)に合わせた農作業プランなど、先人たちが残して来た昔ながらの知恵を活用している。
その一方で、現代農業の論文を読み込んで実践したり、黒糖づくりには糖度計やリトマス試験紙などを、現代科学の目も取り入れて、独自のノウハウを試行している。「伝統農法の知恵はもちろん大切ですが、ぼくらに足りない経験値を補うためには、現代技術んp力にも頼っているんですよ」
3ー循環する農業
畑の隣に鶏舎が並び、800羽のニワトリが平飼いされている。この鶏舎は広々としてニワトリたちが自由に走り回っている。
この鶏たちには外国産飼料は一切与えず、米ぬか、泡盛の酒カス、魚のアラ、青草、おから、米、麦、ミネラルを用いて作った発酵飼料で育てている。
「ここで取れる鶏糞も、畑には大事な肥料になります。鶏舎の土には有用微生物も自然発生しますから、これが堆肥の発酵に役立っているんです」
そしてまた、畑の草が鶏のエサになる。
4ー約2年かける堆肥づくり
農水苑・虹で作っている堆肥は、約2トンを常備している。前田さんたちが、いかに土づくりを大切にしているかが、その大きなストックヤードを見ても分かる。
「堆肥は、バガス(サトウキビの葉や搾りかす)、牛糞、鶏糞、伐採木のチップ、養鶏場から出る優れた堆肥が中心。それに海砂混ぜ、有機微生物用いて約2年熟成させてから使っています」
堆肥といえば臭いと思いがちだが、ここの堆肥は十分発酵させているからか、全く臭くない。それどこか、鰹節の様な旨味成分の美味しいそうな匂いがするのである。

前田さんが目指す循環農業のあり方
尚、3月8日(日)11時〜16時 農水苑・虹 収穫祭虹のまつりが開催されます。お気軽に参加して下さい。
農水苑は一言でいうとどんなところなのでしょうか?いきなりこんな質問から番組はスタート致しました。

農水苑について語る前田英章さん
琉球新報2019年2月19日に次の様な記事が掲載されていました。農水苑のごく一面なのですが、引用させて頂きました。
糸満市新垣で外国産飼料を使わず、自ら作った発酵飼料で鶏を育てて、卵を販売している「農水苑・虹」(前田英章代表)の、新しい卵のパッケージが完成した。8月16日、デザインの基になった絵を描いた子どもたちを「虹」に招いて、お披露目会が開かれた。

お披露目会に参加した子どもたちとデザインを担当した「デコール」の瑞慶山成人さん(右端)と亜矢子さん(右から2人目)、農水苑・虹の前田英章さん(中央)=糸満市新垣の農水苑・虹
新しく完成したパッケージは「虹」に日頃から遊びに来ている子どもたちが、「虹」で働く人たちや鶏をイメージして書いたイラストを基に、豊見城市でデザイン事務所「デコール」を営む瑞慶山成人さん(39)亜矢子さん(39)夫妻がデザインした。

パッケージを手に取った藤井橙子さん(6)は「イラストがかわいいパッケージになってうれしい。お店に並んでいるのを見るのが楽しみ」と話した。
前田さんは「子どもたちのエネルギーがいっぱい詰まった絵で包まれた卵は、食べる人も元気になると思う」と顔をほころばせた。
亜矢子さんは「子どもたちだからこそ描ける絵がとてもすてきだった。いろんな人に手に取ってもらいたい」と話した。

冒頭の質問は言い換えれば、前田さんが目指す農業とは何かという事になる。
1ー作物本来の力引き出す
教育や環境、平和、エネルギーなど、現代が抱える問題に対処するには、新しい価値観でライフスタイを再構築するべきだと前田さんは考えた。循環型で化学肥料を使わない、自然に無理を押し付けない農業で、本来の力を引き出そうと考え実践する農業を目指している。
2ー科学的な目を持って
農水苑・虹の畑では、化学肥料や農薬を使わない代わり、堆肥づくりや海砂を土にすき込む伝統的な土壌づくり、大陰暦(旧暦)に合わせた農作業プランなど、先人たちが残して来た昔ながらの知恵を活用している。
その一方で、現代農業の論文を読み込んで実践したり、黒糖づくりには糖度計やリトマス試験紙などを、現代科学の目も取り入れて、独自のノウハウを試行している。「伝統農法の知恵はもちろん大切ですが、ぼくらに足りない経験値を補うためには、現代技術んp力にも頼っているんですよ」
3ー循環する農業
畑の隣に鶏舎が並び、800羽のニワトリが平飼いされている。この鶏舎は広々としてニワトリたちが自由に走り回っている。
この鶏たちには外国産飼料は一切与えず、米ぬか、泡盛の酒カス、魚のアラ、青草、おから、米、麦、ミネラルを用いて作った発酵飼料で育てている。
「ここで取れる鶏糞も、畑には大事な肥料になります。鶏舎の土には有用微生物も自然発生しますから、これが堆肥の発酵に役立っているんです」
そしてまた、畑の草が鶏のエサになる。
4ー約2年かける堆肥づくり
農水苑・虹で作っている堆肥は、約2トンを常備している。前田さんたちが、いかに土づくりを大切にしているかが、その大きなストックヤードを見ても分かる。
「堆肥は、バガス(サトウキビの葉や搾りかす)、牛糞、鶏糞、伐採木のチップ、養鶏場から出る優れた堆肥が中心。それに海砂混ぜ、有機微生物用いて約2年熟成させてから使っています」
堆肥といえば臭いと思いがちだが、ここの堆肥は十分発酵させているからか、全く臭くない。それどこか、鰹節の様な旨味成分の美味しいそうな匂いがするのである。

前田さんが目指す循環農業のあり方
尚、3月8日(日)11時〜16時 農水苑・虹 収穫祭虹のまつりが開催されます。お気軽に参加して下さい。
Posted by 高橋進 at 01:27│Comments(0)
│ビタミンFM