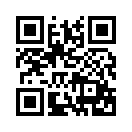2012年04月23日
有機野菜を語る。中村一敬

先週に引き続き、4月21日の糸満CFM「ビタミンFM」は、初の農業経営者で糸満にある有機農園ファームなかむら代表の中村一敬さんをお招きしてお送りいたしました。
先週の話の中で一番印象的だったのは、援農をやって参加した人が元気になって帰っていくといったことなのですが、今週は、野菜の安全・安心についてお聞きしたいと思います。安全・安心の一番のキィーワードは「地産地消」ということになるのと思いますが。
有機農業だから安全であるといよりも、自分は「なぜ野菜を作るのに農薬が必要なのか」ということに疑問を感じたのです。野菜を農薬無しで作ってみたらどうかと思ったのです。形は不揃いですが作れた。そのことが原点なのです。
3,11以降、特に原発事故により東日本の野菜は放射能に汚染されているといった消費者の心理があり、西日本の野菜を求めるといった動きがあった訳ですが、沖縄はさらに福島の原発から遠く離れている。日本で一番の低汚染地域が沖縄なのです。有機野菜に限った訳ではないのですが、沖縄で作られた野菜は確実に需要があると思ったのです。
沖縄の野菜は高い。さらに有機野菜はもっと高いのではないか?
沖縄の野菜の自給率は10%、さらに有機野菜はその内の1%も満たない訳です。
先週「援農」についてお話をしたのですが、手間が非常にかかる。
農薬を使った際の例として宮崎県の農産物栽培「慣行基準」に基く農薬散布回数は、多い順に、ナス74回、トマト62回、ピーマン62回、いちご60回、きゅうり50回(以上、促成栽培)という水準です。露地での栽培ではナス36回、トマト46回、きゅうり42回と半減とはいいませんが減少します。
農薬を使わない分、人手によって虫をとり、雑草を抜くなどが必要になります。有機野菜を作っている自分としたら値段が高いとは思っていません。その分コスト(手間)が掛かっているということです。
それと同時にコストが高いということを消費者に説明する努力が必要ではないかと思っています。
「しまのくんち」についてお聞きしたいのですが
「しまのくんちえ」とは島の元気といった意味なのですが、有機野菜を作る生産グループで現在30名います。南は僕のところの糸満から、北は大宜味村までの農家が集まったグループです。
「しまのくんち」としてグループに参加しない農家の方もいると思いますが、「しまのくんち」毎月1回集まって勉強会を開いています。年に一回か二回位は本土から有機農業をやっている方を招いて勉強会をしたりしています。昨年は「奇跡のりんご」で有名な木村さんを招いて公民舘で開催したりしました。この場合は有機農産物の生産農家だけではなく、興味のある方であれば参加できるように致しました。
今後の課題として何があげられますか。
先程から高橋さんがいっているとおり、消費者に対する説明が不足しているのではないか。スーパーに行っても自分の栽培した野菜が売られていないといったことは、ただたんに流通の問題だけではなく、生産者がただ作っただけで、流通に乗せるための努力をしていなかったのではないかと思ったのです。おもろまちで
有機野菜を販売していた時に、「この野菜は何処へ行ったら買えるの」と聞かれたのです。まさに、そこにヒントがあったのです。ただ野菜を作るだけではなく、売る場所を作ったり、有機農産物とは何かを説明できるような仕組みを作る必要があると思っています。
定期的に消費者と生産者が一同に会した場所を作っていくことではないか。
保育園を使って「食育」と合わせて特売所を作りたいですね。幼い子供のころから農薬付けの野菜を食べることによって大きくなった時に様々な病気になったりする。子供の頃から安心・安全な野菜を食べて頂きたいと思っています。
中村さんの夢は何ですか?
農業を中心とした社会を作りたい。例えばピザ屋さんのような、自分で作った有機野菜を使ったピザを食べてもらったり、有機野菜の直売所であったり、消費者と生産者が作るコミュニティーのようなものを作りたいと思っています。
二週間にわたってありがとうございました。
Posted by 高橋進 at 21:54│Comments(0)
│ビタミンFM