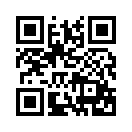2012年03月28日
iPhoneの作り方 米スタンフォード大学が始めた「驚異の授業」
一昨日、琉球新報のコラム「南風」を書いてた仲村知之(香港在投資会社勤務)さんに色々お話を聞いた。
仲村さんとは、NHK沖縄の復帰40周年企画で、海外で活躍する沖縄人の方を紹介する番組の企画でコラムを読んで非常に興味を持ち、お会いしたく、何度かメールのやり取りしている内に「明日沖縄に・・・。」とメールが入っており
早速、お話を伺いに出かけた。
何故、iPhoneの作り方と仲村さんと話が一緒なのかということ、ここでいうデザイナーの概念『サービスを生み出すまでのプロセスを再構築できる能力を備えた人材で、彼らは広義の「デザイナー」と称されている。』
仲村さんの頭の中に、地図がり、香港を中心とした東南アジア、インドを含む地図がある。その地図には、香港の投資会社で培われた経済の概念がある。
香港人は文化大革命を逃れて中国から香港にそれこし「着の身着のまま」で中国大陸から避難してきた人々によってつくられ、1997年の香港の中国返還の際に「中国化」を恐れて海外へ移民し、その資産を分散し、住む場所すら複数の国家にまたがっているというのが香港人だと仲村さんは言うのです。
そして、現在、投資会社勤務の関連でインド・東南アジアを結ぶ光ファイバー網の邦人代表としての顔を持っている。
沖縄は過去、現在を語らる人は多くいるが、未来を語る人が極端にすくないのはどうしてですかと・・・。
水に例えると、水は高きところから低いところに流れてい来る。それが、一時は中国であり、またある時はアメリカであったり、日本であったりする。沖縄から水が中国であったり、アメリカであったり、日本に流れる事が無かったのではないか。つまり、未来を語るというのは、沖縄から世界に水の流れを作ることであり、デザインすることでもあるのではないかと僕は考えた。
光ファイバー網の構想は当初、日本は含まれていなかった。「ものづくりというのは、既に、韓国であったり、中国であったりする訳だけど、日本には世界に誇るものがあるとすればコンテンツではないか」という事に気が付いたというのだ。
仲村さんの話は、国境や言語、宗教を乗り越えてすすむボーダレスの経済活動は、僕らの次の世代が成し遂げることができるものがあるというのだ。その為には、140万人の県民の半分位の人々が海外に出るというようなことではないかと・・・。冗談のように笑った。
日経ビジネスより転載
仲村さんとは、NHK沖縄の復帰40周年企画で、海外で活躍する沖縄人の方を紹介する番組の企画でコラムを読んで非常に興味を持ち、お会いしたく、何度かメールのやり取りしている内に「明日沖縄に・・・。」とメールが入っており
早速、お話を伺いに出かけた。
何故、iPhoneの作り方と仲村さんと話が一緒なのかということ、ここでいうデザイナーの概念『サービスを生み出すまでのプロセスを再構築できる能力を備えた人材で、彼らは広義の「デザイナー」と称されている。』
仲村さんの頭の中に、地図がり、香港を中心とした東南アジア、インドを含む地図がある。その地図には、香港の投資会社で培われた経済の概念がある。
香港人は文化大革命を逃れて中国から香港にそれこし「着の身着のまま」で中国大陸から避難してきた人々によってつくられ、1997年の香港の中国返還の際に「中国化」を恐れて海外へ移民し、その資産を分散し、住む場所すら複数の国家にまたがっているというのが香港人だと仲村さんは言うのです。
そして、現在、投資会社勤務の関連でインド・東南アジアを結ぶ光ファイバー網の邦人代表としての顔を持っている。
沖縄は過去、現在を語らる人は多くいるが、未来を語る人が極端にすくないのはどうしてですかと・・・。
水に例えると、水は高きところから低いところに流れてい来る。それが、一時は中国であり、またある時はアメリカであったり、日本であったりする。沖縄から水が中国であったり、アメリカであったり、日本に流れる事が無かったのではないか。つまり、未来を語るというのは、沖縄から世界に水の流れを作ることであり、デザインすることでもあるのではないかと僕は考えた。
光ファイバー網の構想は当初、日本は含まれていなかった。「ものづくりというのは、既に、韓国であったり、中国であったりする訳だけど、日本には世界に誇るものがあるとすればコンテンツではないか」という事に気が付いたというのだ。
仲村さんの話は、国境や言語、宗教を乗り越えてすすむボーダレスの経済活動は、僕らの次の世代が成し遂げることができるものがあるというのだ。その為には、140万人の県民の半分位の人々が海外に出るというようなことではないかと・・・。冗談のように笑った。
日経ビジネスより転載
アップル、グーグル、フェイスブックなどが本社を構える、インターネット大手の集積地。当時はフェイスブックが約50億ドルの株式公開に踏み切ったニュースもあって、華やかさと活気に満ちていた。ここだけは、リーマンショック後に停滞した米国経済の苦境とは別世界だ。
そんなシリコンバレーでは、フェイスブックの次を狙う新興(スタートアップ)企業が次々と立ち上がっている。
彼らを取材する中で、ある面白い話題を耳にした。現地の多くの企業がここ数年、人材を採用する際に重視しているのが、「デザイン」能力なのだという。
といっても、いわゆる製品やサービスの見た目のみを手がける専門職ではない。
「顧客が何を必要としているのか。本当に必要な製品は何か。それらを紡ぎ出し、製品・サービスの機能にまで落とし込める人材」。iPadやiPhone向けにソーシャルマガジンと呼ばれるアプリケーション「Flipboard」を開発した、同社のマイク・マキューCEOは言う。
いわば、サービスを生み出すまでのプロセスを再構築できる能力を備えた人材で、彼らは広義の「デザイナー」と称されている。
例えば、アップルのiPhoneは、利用者が日々持ち歩く携帯電話を再定義した。持ち歩ける小型の情報端末として位置づけ、通話は数ある機能の1つと位置づけ直した。
そうして再定義した端末を、いかにして利用してもらうか。操作の流れ、ボタンの配置、画面の構成、効果音など、細部にまできめ細かく設計し、顧客が利用しやすい形に変えていく。こうした一連の作業の全体像を描ける能力を、シリコンバレー企業の多くが求めている。
.
Posted by 高橋進 at 11:52│Comments(0)
│エピソード