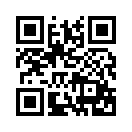2016年04月22日
排除せず共生の視点を
4月14日沖縄タイムスホールでひらかれた「未来を支える~みえてきた子どもの貧困」
シンポにて、この問題を取材をつづけているタイムス記者田嶋正雄氏の発言が気に
なり、その発言の概要を振り返ってみよう。
現在の貧困は貧乏とイコールではない。単に経済的な貧しさでは昔の方が貧しかった。
物や情報があふれる社会で、周りが持っている物や情報を持てず、孤立したり疎外感を
感じたりしているのが現在の貧困だ。
「どうせ駄目だ、無理だ」が口癖になり、自己肯定感が低い子どもが多い。
全部がそうだと言わないが、学校で排除の論理が目立つ。校則違反の子を校門で
追い返す例もまだある。この子たちを排除しても社会からいなくなる訳ではない。
同時代を生きる仲間、共生の視点が必要だ。
名護市の中学校では、排除せず、学校を学び合いの授業、みんなが参加できる授業
で学校づくりを進め、不登校の生徒が劇的に減っている。必ずしも子ども貧困対策で
やっている訳ではないが、結果的に貧困対策で大きな成果を上げている。
ここに大きなヒントがあるのではないか。
2008年、就学前から大学まで教育費を負担しているフィンランドへ取材に行き、
教育省高官にインタビューをいた。なぜ教育が政策の最優先なのか問うと、「一人の
子どもが大人になった時、自立した納税者になるのか、福祉に頼って生きるのか、
福祉に頼る層が大きくなると国は成り立たない。それを左右するのが教育だ」と答えた。
オフレコでは、「日本と韓国は世界的にみても教育費の私費負担が大きすぎて、諦める
子どもが多い社会だと自分たちはみている。その国の将来がどうなってるか注目している」
と言っていた。7~8年たち、そういう状況になっていると感じる。
子ども貧困には共感の声が寄せられているが、かわいそうではなく、人権問題であり、
自分たちの社会を今後どうするかという視点が重要だ。自己責任にしてしまうと現在の
貧困の状況が次世代へ引き継がれる。どこかで止めないといけな。
下線を引いたところが気になり、調べることにした。
名護の中学校とは?
2015年11月24日 沖縄タイムス「学び合い 育む意欲 どの子も排除しない■不登校を減らす」
フィンランドの教育行政とは?
シンポにて、この問題を取材をつづけているタイムス記者田嶋正雄氏の発言が気に
なり、その発言の概要を振り返ってみよう。
現在の貧困は貧乏とイコールではない。単に経済的な貧しさでは昔の方が貧しかった。
物や情報があふれる社会で、周りが持っている物や情報を持てず、孤立したり疎外感を
感じたりしているのが現在の貧困だ。
「どうせ駄目だ、無理だ」が口癖になり、自己肯定感が低い子どもが多い。
全部がそうだと言わないが、学校で排除の論理が目立つ。校則違反の子を校門で
追い返す例もまだある。この子たちを排除しても社会からいなくなる訳ではない。
同時代を生きる仲間、共生の視点が必要だ。
名護市の中学校では、排除せず、学校を学び合いの授業、みんなが参加できる授業
で学校づくりを進め、不登校の生徒が劇的に減っている。必ずしも子ども貧困対策で
やっている訳ではないが、結果的に貧困対策で大きな成果を上げている。
ここに大きなヒントがあるのではないか。
2008年、就学前から大学まで教育費を負担しているフィンランドへ取材に行き、
教育省高官にインタビューをいた。なぜ教育が政策の最優先なのか問うと、「一人の
子どもが大人になった時、自立した納税者になるのか、福祉に頼って生きるのか、
福祉に頼る層が大きくなると国は成り立たない。それを左右するのが教育だ」と答えた。
オフレコでは、「日本と韓国は世界的にみても教育費の私費負担が大きすぎて、諦める
子どもが多い社会だと自分たちはみている。その国の将来がどうなってるか注目している」
と言っていた。7~8年たち、そういう状況になっていると感じる。
子ども貧困には共感の声が寄せられているが、かわいそうではなく、人権問題であり、
自分たちの社会を今後どうするかという視点が重要だ。自己責任にしてしまうと現在の
貧困の状況が次世代へ引き継がれる。どこかで止めないといけな。
下線を引いたところが気になり、調べることにした。
名護の中学校とは?
2015年11月24日 沖縄タイムス「学び合い 育む意欲 どの子も排除しない■不登校を減らす」
フィンランドの教育行政とは?
Posted by 高橋進 at 12:01│Comments(0)
│子どもの貧困