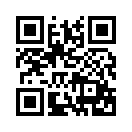2016年07月09日
地域活性化と雇用拡大について
糸満市に「糸満市の観光の魅力と滞在型観光の商品化についての私の提案」作文800字を6月の下旬に提出して、一昨日、糸満市役所に伺ってお話をさせていただきました。
この作文は、まず、就労に対する一般的な意識について特に、若者の就労について、最近のデーターからすると一次産業従事したいと答えたのが、21%で花形のIT産業が8%であるというデーターを元に、雇用の重点を一次産業とし、一次産業を中心とした六次産業化による雇用の創出を作り出すといったことを目標とする。
南城市は耕作破棄地を使って雇用と産業を作ることを主眼として、ミツバチを使った南城市全体を食べられる景観づくりと名産づくりを目指すものとして久しぶりにワクワクして作文を書きました。ただし、400字原稿用紙1枚で農業問題と雇用問題の解決策を書くというのは非常に難しいもので400字で課題解決策が書けるような問題でもないと思いましたが何か今後の地域づくりの役に立てばと思い南城市に提出いたしました。
(ミツバチから教えてもらったこと)。
この案は見事没でした。
それに続く糸満市の雇用問題と空き部屋対策といったものを観光の視点でまず、課題の抽出そして、その課題の解決策をということなのですが、そもそも僕が取り組む課題として「糸満市の観光の魅力と滞在型観光の商品化についての私の提案」というテーマについて800字の作文を提出するといったものでした。
そもそも、この南城市と糸満市の二市がこのような募集を同じ時期に行ったというのは後の新聞発表で分かったことなのですが、厚生労働省が2016年度の実践型地域雇用創造事業に糸満市地域雇用創造推進協議会と南城市地域雇用創造協議会を選び、採択通知書を両協議会に交付した。
ここでは糸満市での取組みについて、空き家の宿泊施設化や農業、マリンレジャーといった体験観光に従事する人材を育成する事業を通じて、153人の雇用を図るとなっている。
僕が書いたテーマとは随分違った内容が報道されており、それに向けて作文の書きなおす訳にもいかず。
糸満市役所にうかだった次第です。
南城市と糸満市の共通した僕の考え方は、すごくシンプルなものです。例えば、読谷の農業とりわけ紅イモ生産の農家のキロ当たりの買取り価格が100円で紅イモタルトの原料を買い上げている。鹿児島の芋焼酎の芋の買取り価格が350円。そこの違いは何かといったことが雇用とか特産品つくる上で重要なことと思いるのです。
資本主義ということを考えると、生産者の買取り価格を抑えて100円で買う。そして、その100倍の価値を作りだすというのが六次産業化と言えるのですが、僕のブログでは御菓子御殿の中でそのことを学ぼうと呼び掛けているのですが、僕の気持ちからすると、農家はそれで良いのですか?いつまでも100円で原料の紅イモを作って売っているというのではなく、農家そのものが紅イモタルトを作り100倍の価値を作りだすといこととが六次産業化というのこではないかということなのです。
また、単に350円で芋を売るといった条件闘争委を農家がするべきだと主張しているのではなく、このプロジェクトが資本主義のルールの中で原料や賃金を安く抑えて製造するといった従来型の生産では、誰も幸せになれないし、沖縄の子どもを貧困から救うこともできないということを言いたいのです。つまり、紅イモを作る農家も幸せであり、紅イモタルトを作る会社も幸せである。そこで働く従業員も幸せであるということが、しいては読谷全体を変え、沖縄全体を変えていく。そのような産業構造を作るといったことが何よりも必要なのではないかと思うのです。
資本主義の勝利は社会主義国家の崩壊の中でゆるぎないものとなっています。
資本主義の真っ只中で、僕はこう叫びたかったのです。原料を100円ではなく、その10倍の価格で買い取り、農業に従事している方の未来に幸せを作りだす。そして、その材料を人と手間をかけて高付加価値の特産品を作る。つまり、人と手間をかけるということが雇用を作りだ出すということではないか。南風原町ではミツバチが受粉したカボチャが通常のカボチャの10倍の価格で売られている。
そのことを考えると、南城市で提案したミツバチを真ん中にした政策を糸満市でも展開していく。
エコロジカルな農業へ、ミツバチが生育できる農業へ転化して、南城市でのオープンガーデンを蜜源とした食べられる景観を作り、
それを高く買い上げ、蜂蜜と組み合わせた名産を作りだすといったプランをこの糸満市で実現できたらとの提案をしました。
糸満で放送しているビタミンFMは、このような趣旨で幸せな家庭が幸せな地域を作り、幸せな組織が幸せな社会を作る。
その幸せのドミノ倒しの一個の駒として、なれればと思い、電波に乗せて6年間放送しています。
糸満から沖縄を変えよう。糸満から日本を変えよう。糸満から世界を変えよう。幸せの連鎖が生まれる雇用と産業を作りだすプランを実現したいのです。と、プレゼンをいたしました。
地域おこしや魅力を再発見するには、昔から「若者、よそ者、バカ者」と言われていますが、僕は既に若者ではなく、44年間も沖縄に住んでいて、よそ物ともあまりいえない。そして残ったのが、バカ者。このバカ者の発想を是非、役立てたいと思っています。
糸満市の地域活性化はまず、糸満に眠る輝ける宝を発見しなければなりません。何気に普段気にもとめていないもの、よそ者の目からしたらそれは糸満だけにある宝ものということもある。糸満に移住した他府県人や外国人を地域おこし雇用拡大応援隊としてアドバイスを頂くこと。そして、糸満の市民に聞いてみるというこはどうだろう。
富山県氷見市の部長にお会いしたことがある。この氷見市ではドリームプラン・プレゼンティションが地域おこしの重要な柱となっている。
夢を語り、その夢を応援する市民が協力して地域おこしをおこなっているのである。
ならば、糸満市民の夢を聞いてみる。そして、このプロジェクトがその夢実現を推進することによって、産業と雇用を作る。むしろ市民の黒子として
応援していく。3年で153名、1年で51名の雇用を作ることは、あながちこういった取組みを継続することが遠回りのようで近道ではないかと考えているが・・・。
これも没かな!
結果発表は13日です。
この作文は、まず、就労に対する一般的な意識について特に、若者の就労について、最近のデーターからすると一次産業従事したいと答えたのが、21%で花形のIT産業が8%であるというデーターを元に、雇用の重点を一次産業とし、一次産業を中心とした六次産業化による雇用の創出を作り出すといったことを目標とする。
南城市は耕作破棄地を使って雇用と産業を作ることを主眼として、ミツバチを使った南城市全体を食べられる景観づくりと名産づくりを目指すものとして久しぶりにワクワクして作文を書きました。ただし、400字原稿用紙1枚で農業問題と雇用問題の解決策を書くというのは非常に難しいもので400字で課題解決策が書けるような問題でもないと思いましたが何か今後の地域づくりの役に立てばと思い南城市に提出いたしました。
(ミツバチから教えてもらったこと)。
この案は見事没でした。
それに続く糸満市の雇用問題と空き部屋対策といったものを観光の視点でまず、課題の抽出そして、その課題の解決策をということなのですが、そもそも僕が取り組む課題として「糸満市の観光の魅力と滞在型観光の商品化についての私の提案」というテーマについて800字の作文を提出するといったものでした。
そもそも、この南城市と糸満市の二市がこのような募集を同じ時期に行ったというのは後の新聞発表で分かったことなのですが、厚生労働省が2016年度の実践型地域雇用創造事業に糸満市地域雇用創造推進協議会と南城市地域雇用創造協議会を選び、採択通知書を両協議会に交付した。
ここでは糸満市での取組みについて、空き家の宿泊施設化や農業、マリンレジャーといった体験観光に従事する人材を育成する事業を通じて、153人の雇用を図るとなっている。
僕が書いたテーマとは随分違った内容が報道されており、それに向けて作文の書きなおす訳にもいかず。
糸満市役所にうかだった次第です。
南城市と糸満市の共通した僕の考え方は、すごくシンプルなものです。例えば、読谷の農業とりわけ紅イモ生産の農家のキロ当たりの買取り価格が100円で紅イモタルトの原料を買い上げている。鹿児島の芋焼酎の芋の買取り価格が350円。そこの違いは何かといったことが雇用とか特産品つくる上で重要なことと思いるのです。
資本主義ということを考えると、生産者の買取り価格を抑えて100円で買う。そして、その100倍の価値を作りだすというのが六次産業化と言えるのですが、僕のブログでは御菓子御殿の中でそのことを学ぼうと呼び掛けているのですが、僕の気持ちからすると、農家はそれで良いのですか?いつまでも100円で原料の紅イモを作って売っているというのではなく、農家そのものが紅イモタルトを作り100倍の価値を作りだすといこととが六次産業化というのこではないかということなのです。
また、単に350円で芋を売るといった条件闘争委を農家がするべきだと主張しているのではなく、このプロジェクトが資本主義のルールの中で原料や賃金を安く抑えて製造するといった従来型の生産では、誰も幸せになれないし、沖縄の子どもを貧困から救うこともできないということを言いたいのです。つまり、紅イモを作る農家も幸せであり、紅イモタルトを作る会社も幸せである。そこで働く従業員も幸せであるということが、しいては読谷全体を変え、沖縄全体を変えていく。そのような産業構造を作るといったことが何よりも必要なのではないかと思うのです。
資本主義の勝利は社会主義国家の崩壊の中でゆるぎないものとなっています。
資本主義の真っ只中で、僕はこう叫びたかったのです。原料を100円ではなく、その10倍の価格で買い取り、農業に従事している方の未来に幸せを作りだす。そして、その材料を人と手間をかけて高付加価値の特産品を作る。つまり、人と手間をかけるということが雇用を作りだ出すということではないか。南風原町ではミツバチが受粉したカボチャが通常のカボチャの10倍の価格で売られている。
そのことを考えると、南城市で提案したミツバチを真ん中にした政策を糸満市でも展開していく。
エコロジカルな農業へ、ミツバチが生育できる農業へ転化して、南城市でのオープンガーデンを蜜源とした食べられる景観を作り、
それを高く買い上げ、蜂蜜と組み合わせた名産を作りだすといったプランをこの糸満市で実現できたらとの提案をしました。
糸満で放送しているビタミンFMは、このような趣旨で幸せな家庭が幸せな地域を作り、幸せな組織が幸せな社会を作る。
その幸せのドミノ倒しの一個の駒として、なれればと思い、電波に乗せて6年間放送しています。
糸満から沖縄を変えよう。糸満から日本を変えよう。糸満から世界を変えよう。幸せの連鎖が生まれる雇用と産業を作りだすプランを実現したいのです。と、プレゼンをいたしました。
地域おこしや魅力を再発見するには、昔から「若者、よそ者、バカ者」と言われていますが、僕は既に若者ではなく、44年間も沖縄に住んでいて、よそ物ともあまりいえない。そして残ったのが、バカ者。このバカ者の発想を是非、役立てたいと思っています。
糸満市の地域活性化はまず、糸満に眠る輝ける宝を発見しなければなりません。何気に普段気にもとめていないもの、よそ者の目からしたらそれは糸満だけにある宝ものということもある。糸満に移住した他府県人や外国人を地域おこし雇用拡大応援隊としてアドバイスを頂くこと。そして、糸満の市民に聞いてみるというこはどうだろう。
富山県氷見市の部長にお会いしたことがある。この氷見市ではドリームプラン・プレゼンティションが地域おこしの重要な柱となっている。
夢を語り、その夢を応援する市民が協力して地域おこしをおこなっているのである。
ならば、糸満市民の夢を聞いてみる。そして、このプロジェクトがその夢実現を推進することによって、産業と雇用を作る。むしろ市民の黒子として
応援していく。3年で153名、1年で51名の雇用を作ることは、あながちこういった取組みを継続することが遠回りのようで近道ではないかと考えているが・・・。
これも没かな!
結果発表は13日です。
Posted by 高橋進 at 11:46│Comments(0)
│地域活性化