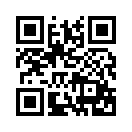2011年06月03日
被災地の人々に、彼方(希望)の灯火を燈そう!
昨日の不信任決議の与野党の動きと、その後の採決をテレビで見ながら、つくづく思う。一体、この国の政治家はと。いてもたってもいられない気持ちだ。先程まで、在沖縄岩手県人会の会長の加賀哲彦さんと東北関東大震災復興支援フリーペーパーの「風の便り」発行や復興支援の活動を進めている沖縄大学の稲垣暁さんと打ち合わせをしてきた。沖縄で出来る支援活動はなかと色々話をしてきたのだが、3日前に岩手から帰ってきた加賀さんは、車で被災地に入る際に、坂道を下りて行くと瓦礫と化した街が現れ、坂を上ると見慣れた岩手の風景がある。車が坂道を下ると又、瓦礫とかした街が現れる。その繰り返しの中で、坂を下るのが怖くなって来たと言った。そして、被災地には、活力とか復興といったものとはかけ離れた現実があった。それは、無気力感といったものが被災地に漂っていると。永田町と霞が関のパワーゲームとは無縁の現実が被災地にある。今、被災者に必要なのは、霞が関が描いた構想ではなく、「遠くに見える灯火に励まされ」る。人の心の闇と現実の闇を照らす灯火ではないか。加賀さんの話を聞きながら五木寛之の著「人生の目的」の文章を思い出した。『<中略>いま私が暗闇の山道を、重い荷物を背負って歩いているする。行く手は夜にとけこんで、ほとんど一寸先も見えない。手探りで歩きつづけるしなない有様だ。目的地も見えない。うしろへ退くこともできない。といって、そのまま座り込んでしまっても、誰も助けに来てくれない。進退きわまっても、行くしかないのだ。手で岩肌をつたいながら、半歩、また一歩とおびえつつ歩く。私たちの生きている様子とは、およそかくのごときのだ。不安と、恐怖と、脱力感で、体がふるえるのを感じる。しかし、そんななかでも、ふと彼方の遠くに、小さな集落の明かりが見えたとしたらどうか。いくべき場所、帰るべき家の灯火が見える。そして、いつか雲間から冴えわたる月光がさしてきて、足元の断崖の道も、山肌も、森も、くっきり浮かびあがる。坂を歩く労苦には変わりない。行く先までの距離がちぢまったわけでもない。荷物が軽くなる訳ではもない。しかし、人は彼方の灯火に勇気づけられ、月光に思わず感謝のため息をつくだろう。そして、ふたたび歩きだす。』
政局の混乱で停滞することなく、小さな事でも、今僕らにできることで、被災地の人々に彼方(希望)の灯火を燈そう!
政局の混乱で停滞することなく、小さな事でも、今僕らにできることで、被災地の人々に彼方(希望)の灯火を燈そう!
Posted by 高橋進 at 20:40│Comments(2)
│東日本大震災支援