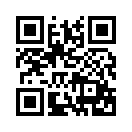2011年08月04日
手紙におもいを込めてかりゆしウエアを送ろう
7月30日(土)のビタミンエフエムは、被災地にかりゆしウエアを手紙を添えて送る活動をしている稲垣 暁さんをお招きしての1時間です。稲垣さんは沖縄大学地域研究所特別研究員として活動をしているのですが、社会福祉文化学科で教鞭をとっている方で、社会福祉文化学科で教えっている学生の中から大震災で被災した人々に何か出来ないかとの声から活動がスタートいたしました。

オープニングトークで、先週7月23日に緊急出演をしたいただいた吉田明彦さんが心配していたとおりのことが沖縄で起きた。それも、糸満市にあるホームセンターカインズの腐葉土が放射線の汚染の疑いがある事がニュースで伝わり、沖縄県知事に10000万名の署名を集めて、汚泥肥料等の県内流入を阻止をと呼びかけた訳ですが、すでに、県内に腐葉土というかたちで流入している事が解り、残念なことですが、オープニングトークでこの事実を伝えることになりました。どう伝えていいのかと考えていたら午後6時の時報が流れ、本来、時報と共に番組のテーマミュージックが流れるのですが、この事を考えていたらテーマミュージックを出すのを忘れてしまい。しばらく無音の異例のスタートとなってしまいました(-_-;)
高橋:何故、被災地にかりゆしウエアを手紙をつけて送ろうというユニークな取り組みは、どの様なことがきっかけで始まったのでしょうか。
稲垣:東日本震災の惨状がメディアによって日本全国に伝わり、学生の中から何か被災者にできないかと自主的な取組として始まりました。GWの休みを活用して、5月初旬に、学生達と岩手県大槌町を訪ね、避難所でボランティアを行った訳なのですが、学生は、特にこの様な状況で、専門的な知識もなく、ケアーをするといっても、何も専門的なことは出来ないのですが、そのような中で何が出来るかを話し合い、被災者に寄りそうことにによって被災者の話を聞くだけでも被災者の心を少しでも軽くする事ができるのではないかと、その活動の中で、高齢の女性のつぶやきがきっかけとなりました。「沖縄の夏服はいいね。古着でいいから送ってくれたらうれしい」と。避難所で沖縄から行った僕らと避難所の皆さんとようやく関係がつくれるようになった頃の事なのです。
被災者は、生き残った自分を責め「もっと辛い立場の人がいる」「色々してもらって申し訳ない」と考えがちで、してもらいたい事や求めていることがあって本音を話してくれない。「欲しい」と本音を話してくてたのが本当にうれしかったですね。
高橋:在沖岩手県人会の代表をしている加賀さんと現地の状況についてお話を伺ったのですが、こんなことを加賀さんは言っていたのですが、仙台からレンタカーを借りて、岩手に入るのですが、今までは子供の頃から見慣れた岩手の山や谷や橋や道が続くのですが、海岸線に近づくにつれ、今までの風景とは一変する。瓦礫と化して街が広がり、その瓦礫を抜けて、道を登っていくと何もなかったような穏やかな岩手の風景になる。道を登ると穏やかな風景、道が降ると瓦礫の街が広がる。何度もその様な道を走るのですが、道を降るのが怖くなってくる。沖縄に帰って来ても道を降るとその情景を思い出し、しばらく、トラウマのようになってしまった。と。
稲垣:当初、ベースキャンプとして、岩手県の内陸部を拠点に情報収集をしていたのですが、バスに乗って沿岸部に近づくと、バスの中が異様な雰囲気になってきます。今まで体験をしたことのない風景が目の前に広がる訳です。その惨状を目にした学生は1日のボランティア活動が終わった夜に2日間泣き続けました。そんな状況の中で、この高齢の女性から「沖縄の夏服」の話があったのです。その日から、夜のミーティングの際に「避難者に足りていないこと」と「自分たちが今何かできること」、そして、「沖縄で出来る事」を表にして書きこんだ訳です。学生もこの様な状況を目の前にして、心理的に大変なストレスがる。夜のミーティングの際は、自分が感じた事を含めて心の内にためこまないために全ての思いを吐き出してもらう事にしました。
そして、その中から自分たちに出来ることが、被災者に寄り添うこと、被災者の心に寄り添い話を聞いてあげること。そして、沖縄に帰ってから「かりゆしウエア」を集めて被災者に送ろうと提案をした訳です。
高橋:学生が被災地と避難所の状況をみて2日間泣き続けたというのは、たとえ沖縄が記憶として沖縄戦といったものを持っているとしても、それは整備された平和の礎であったり、平和資料館であったりする訳ですから、想像力をはるかに越えた、この絶望的な状況とそこに生きる避難所の人たちを目の前にした学生の心理的状況を克服する方法というのをよく思いつきましたね。
稲垣:実は、僕は、阪神大震災の被災者の一人なのです。阪神大震災が起きて僕の場合は、PTSD(心的外傷後ストレス障害 )が5年後に内臓破裂といった症状が出て、緊急入院をして手術をしたという経験があるのです。阪神大震災の被災者の一人として、被災者に何が出来るかという経験を通じてのボランティア活動だったのです。被災地に入った際に、忘れていた大震災の記憶がフラッシュバックして自分も苦しい想いをしたのですが、学生と一緒にその困難を乗り越えていきました。そして、何よりも自分の事よりも被災者に寄り添い話を聞くこと、そばにいてやることが学生と僕に出来るボランティア活動ではなかと思ったのです。阪神大震災の経験から、心のもつれた糸をほぐすといったことに足湯をするといったことがあるのですが、お湯の温度は熱くないですか?と問い掛けるなどを通じて心の糸をほぐすといった活動をしてきました。
高橋:なぜ、かりゆしウエアの古着と手紙なのでしょうか。古着を送るより新しいかりゆしウエアが良いのではと思うのですが。
稲垣:提供者にかりゆしウエアを送ってもらう際に手紙を付けてとお願いしている狙いは、被災者にとって、一次的な避難所から仮設住宅に移るこれからが正念場といえます。阪神大震災の時は、高齢者の孤独死といった起き問題となりましが、受け取った方がこの手紙によって勇気や希望を持ってもらえればと思っています。また、リサイクルと勘違いされことや、不要物が学校に送られてくることを防ぐ。古着はともすれば被災者をみじめな思いにさせる。しかし、一着、一着に思いのこもった手紙が付くと、新品よりも価値が出る。
高橋:大震災の後、宮城県にある日本酒メーカーで「伯楽星」を造っているメーカーの社長に激励のハガキを出したところ、社長から直接電話が掛って来て、蔵を再建にむけて、僕の激励ハガキが事務所に貼ってあり、従業員一同が励みになっているとの電話を頂いたことがありました。いい考えですね。思いをこめて手紙を付けるというのは。
稲垣:被災地の復興には多くの時間がかかる。学生が自然体で社会活動に参画でき、県民が募金以外で継続的に支援できる場づくりの意味もあるのです。7月5日に第一便を送りました。7月7日に160着のかりゆしウエアと手紙が岩手の被災地に届いた。避難所の皆さんが着ている写真とメッセージが届きました。「うちなーちゅになれたでしょうか」着てもらえるか心配をしていた学生も支援と交流の第一歩の喜びを次に向けた新しい活動の灯として行きたいと思います。
高橋:本日はお忙しところありがとうございます。

オープニングトークで、先週7月23日に緊急出演をしたいただいた吉田明彦さんが心配していたとおりのことが沖縄で起きた。それも、糸満市にあるホームセンターカインズの腐葉土が放射線の汚染の疑いがある事がニュースで伝わり、沖縄県知事に10000万名の署名を集めて、汚泥肥料等の県内流入を阻止をと呼びかけた訳ですが、すでに、県内に腐葉土というかたちで流入している事が解り、残念なことですが、オープニングトークでこの事実を伝えることになりました。どう伝えていいのかと考えていたら午後6時の時報が流れ、本来、時報と共に番組のテーマミュージックが流れるのですが、この事を考えていたらテーマミュージックを出すのを忘れてしまい。しばらく無音の異例のスタートとなってしまいました(-_-;)
高橋:何故、被災地にかりゆしウエアを手紙をつけて送ろうというユニークな取り組みは、どの様なことがきっかけで始まったのでしょうか。
稲垣:東日本震災の惨状がメディアによって日本全国に伝わり、学生の中から何か被災者にできないかと自主的な取組として始まりました。GWの休みを活用して、5月初旬に、学生達と岩手県大槌町を訪ね、避難所でボランティアを行った訳なのですが、学生は、特にこの様な状況で、専門的な知識もなく、ケアーをするといっても、何も専門的なことは出来ないのですが、そのような中で何が出来るかを話し合い、被災者に寄りそうことにによって被災者の話を聞くだけでも被災者の心を少しでも軽くする事ができるのではないかと、その活動の中で、高齢の女性のつぶやきがきっかけとなりました。「沖縄の夏服はいいね。古着でいいから送ってくれたらうれしい」と。避難所で沖縄から行った僕らと避難所の皆さんとようやく関係がつくれるようになった頃の事なのです。
被災者は、生き残った自分を責め「もっと辛い立場の人がいる」「色々してもらって申し訳ない」と考えがちで、してもらいたい事や求めていることがあって本音を話してくれない。「欲しい」と本音を話してくてたのが本当にうれしかったですね。
高橋:在沖岩手県人会の代表をしている加賀さんと現地の状況についてお話を伺ったのですが、こんなことを加賀さんは言っていたのですが、仙台からレンタカーを借りて、岩手に入るのですが、今までは子供の頃から見慣れた岩手の山や谷や橋や道が続くのですが、海岸線に近づくにつれ、今までの風景とは一変する。瓦礫と化して街が広がり、その瓦礫を抜けて、道を登っていくと何もなかったような穏やかな岩手の風景になる。道を登ると穏やかな風景、道が降ると瓦礫の街が広がる。何度もその様な道を走るのですが、道を降るのが怖くなってくる。沖縄に帰って来ても道を降るとその情景を思い出し、しばらく、トラウマのようになってしまった。と。
稲垣:当初、ベースキャンプとして、岩手県の内陸部を拠点に情報収集をしていたのですが、バスに乗って沿岸部に近づくと、バスの中が異様な雰囲気になってきます。今まで体験をしたことのない風景が目の前に広がる訳です。その惨状を目にした学生は1日のボランティア活動が終わった夜に2日間泣き続けました。そんな状況の中で、この高齢の女性から「沖縄の夏服」の話があったのです。その日から、夜のミーティングの際に「避難者に足りていないこと」と「自分たちが今何かできること」、そして、「沖縄で出来る事」を表にして書きこんだ訳です。学生もこの様な状況を目の前にして、心理的に大変なストレスがる。夜のミーティングの際は、自分が感じた事を含めて心の内にためこまないために全ての思いを吐き出してもらう事にしました。
そして、その中から自分たちに出来ることが、被災者に寄り添うこと、被災者の心に寄り添い話を聞いてあげること。そして、沖縄に帰ってから「かりゆしウエア」を集めて被災者に送ろうと提案をした訳です。
高橋:学生が被災地と避難所の状況をみて2日間泣き続けたというのは、たとえ沖縄が記憶として沖縄戦といったものを持っているとしても、それは整備された平和の礎であったり、平和資料館であったりする訳ですから、想像力をはるかに越えた、この絶望的な状況とそこに生きる避難所の人たちを目の前にした学生の心理的状況を克服する方法というのをよく思いつきましたね。
稲垣:実は、僕は、阪神大震災の被災者の一人なのです。阪神大震災が起きて僕の場合は、PTSD(心的外傷後ストレス障害 )が5年後に内臓破裂といった症状が出て、緊急入院をして手術をしたという経験があるのです。阪神大震災の被災者の一人として、被災者に何が出来るかという経験を通じてのボランティア活動だったのです。被災地に入った際に、忘れていた大震災の記憶がフラッシュバックして自分も苦しい想いをしたのですが、学生と一緒にその困難を乗り越えていきました。そして、何よりも自分の事よりも被災者に寄り添い話を聞くこと、そばにいてやることが学生と僕に出来るボランティア活動ではなかと思ったのです。阪神大震災の経験から、心のもつれた糸をほぐすといったことに足湯をするといったことがあるのですが、お湯の温度は熱くないですか?と問い掛けるなどを通じて心の糸をほぐすといった活動をしてきました。
高橋:なぜ、かりゆしウエアの古着と手紙なのでしょうか。古着を送るより新しいかりゆしウエアが良いのではと思うのですが。
稲垣:提供者にかりゆしウエアを送ってもらう際に手紙を付けてとお願いしている狙いは、被災者にとって、一次的な避難所から仮設住宅に移るこれからが正念場といえます。阪神大震災の時は、高齢者の孤独死といった起き問題となりましが、受け取った方がこの手紙によって勇気や希望を持ってもらえればと思っています。また、リサイクルと勘違いされことや、不要物が学校に送られてくることを防ぐ。古着はともすれば被災者をみじめな思いにさせる。しかし、一着、一着に思いのこもった手紙が付くと、新品よりも価値が出る。
高橋:大震災の後、宮城県にある日本酒メーカーで「伯楽星」を造っているメーカーの社長に激励のハガキを出したところ、社長から直接電話が掛って来て、蔵を再建にむけて、僕の激励ハガキが事務所に貼ってあり、従業員一同が励みになっているとの電話を頂いたことがありました。いい考えですね。思いをこめて手紙を付けるというのは。
稲垣:被災地の復興には多くの時間がかかる。学生が自然体で社会活動に参画でき、県民が募金以外で継続的に支援できる場づくりの意味もあるのです。7月5日に第一便を送りました。7月7日に160着のかりゆしウエアと手紙が岩手の被災地に届いた。避難所の皆さんが着ている写真とメッセージが届きました。「うちなーちゅになれたでしょうか」着てもらえるか心配をしていた学生も支援と交流の第一歩の喜びを次に向けた新しい活動の灯として行きたいと思います。
高橋:本日はお忙しところありがとうございます。
Posted by 高橋進 at 17:52│Comments(0)
│東日本大震災支援